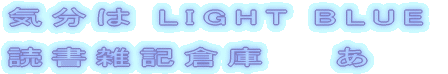
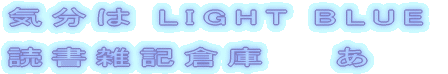
二人の天魔王―「信長」の真実/明石散人/講談社文庫
「第六天魔王」と呼ばれた織田信長の真実の姿を説き明かした一冊。正確な史料の少なさと思い込みや偶像化によって肥大化したイメージを持つ信長とその数々のエピソードの持つ意味を冷静に見つめなおている。そして、信長との対比で、もうひとりの「天魔王」足利義教を再評価しており、それこそが本書の最も重要なメッセージである。籤公方と呼ばれ家臣の手にかかった凡庸な室町将軍という不当に低いイメージを払拭する数々の功績を示して見せ、戦国の天下人たちの先駆者であったことが明かされる。
目からうろこの一冊である。歴史好きといっても本当の意味で史料にあたることなどのない私にとっては、これだけの説得力を持って信長の実像が示されていくのは快感であった。大体戦国武将というのはなぜかビジネス雑誌などで取り上げられイメージが先行し実態が押しつぶされていく傾向があるもので、世の中で取り上げられれば取り上げられるほど大本営発表のように眉に唾しなければいけないものであるが、どうしても先入観の強い信長などは目をくらまされてしまっていたきらいがあった。
しかし、純粋に権力というものを捉えきった足利義教という存在が示されてみると、彼の影響下にあった多くの戦国武将の実像によりちかいものがすかし見えてくる。歴史家というものは、史料にあるものからその裏に存在する実態を見通す力をもった人でなければつとまらないということがよくわかる書である。
(★★★)
人形はこたつで推理する/我孫子 武丸/講談社文庫
幼稚園の保母、妹尾睦月は、園のクリスマス会で、腹話術師朝永嘉夫と彼があやつる人形の鞠小路鞠夫と出会う。この二人が、一人でしゃべり出してしまうマリオネットの助けを借りて、不思議な事件を解決していく。
幼稚園の兎小屋があらされる真相を解く「人形はこたつで推理する」、公演中の劇団のテントのなかで出演者の一人が撲殺される事件を解決する「人形はテントで推理する」など4編の短編を収録。どれもびっくりはしないが気のきいた小品が並べられている。
おどろおどろしくなりがちなミステリの中にあっては、登場人物のキャラクターと探偵の設定の妙で明るい雰囲気を維持できている(事件は決してほのぼのとしたものではないが)。大長編全盛の時代だが、ミステリーでこの位の長さの短編小説がもっとあってもよいと思うのだが。
(★)
りら荘事件/鮎川哲也/講談社文庫/エンタ
貿易商・星影龍造ものの代表作。日本芸術大学の施設「りら荘」、そこに夏のある日、互いに愛憎の交錯する七名の学生−−日高鉄子、行武栄一、橘秋夫、安孫子宏、松平紗絽女、尼リリス、牧数人−−が訪れる。第一日目の夜、橘と紗絽女が婚約を発表する。それぞれに思いを寄せていた鉄子と安孫子は意気消沈する。翌日、リリスのコートを持った人物が山奥で足を滑らせて亡くなる。そして現場には別荘から持ち出されたカードの「スペードのA」。その後りら荘でも、紗絽女が衆人環視の中で毒殺、釣りをする橘が刺殺と事件が立て続けに発生、前の事件と同様にカードが現場から発見される。さらに殺人事件が連続していく。
「本格」推理小説としては悪くない味である。トリックもふんだんに盛り込まれており、解決もきれいに決まっている。しかしながら、小説として読んだときの物足りなさがある。坂口安吾の「不連続殺人事件」もそうだが、犯人当て懸賞小説のようで、どうにも読後の達成感がない。米国黄金期の本格だって骨格は同じなわけで、不必要なまでの装飾はまさにこうした読後感を醸成するためにあったのだろうか。小説は、あるカテゴリのものはその固有の楽しみ方だけで味わうと決まっているわけではない。むしろその固有の楽しみ方しかないとすれば、それゆえの踏み込み甲斐のなさが問題となるかもしれない。
(★ 1999)
朱の絶筆/鮎川哲也/講談社文庫
貿易商・星影龍造もの。人気作家篠崎豪輔は傲岸不遜な性格故若き日には、多くの人々を苦しめ破滅に追いやることにも罪悪感を持たない男であった。年老いた篠崎は軽井沢の別荘にこもり執筆する暮らしを送っていた。ある日、豪輔は午睡の最中、何者かにカーテンの紐によって絞殺される。偶然にも、その日は過去に豪輔からひどい仕打ちを受け彼に対し殺意を持つ人間が集まっていた。
物語をとおして篠崎豪輔のひととなりや彼を巡る人物たちの行動や愛憎が描かれていくのだが、それは集まっている人々にすべて動機があるということを示すためのファンクションでしかない。「本格」としてはそれでよいのだが、せっかくこうしたファンクションがあるのであれば、ここに厚みをもたせることもできたであろうに。結末の謎解き部はさすが巨匠鮎川。
(× 1999)
月光ゲーム―Yの悲劇’88/有栖川有栖/創元推理文庫
英都大学の推理小説研究会に入った一回生の有栖川有栖は、この小さなミステリ愛好家の集まりを楽しんでいたが、その夏、遊び半分のキャンプで矢吹山へ行くこととなる。そこで、同様の学生グループと出会い楽しいキャンプとなったのだが、一人の女子大生が黙って下山する事件が起きるとともに、突然休火山の矢吹山が噴火し彼らのキャンプ地は下界と途絶した状態となってしまう。この極限状態の中、連続殺人事件が発生する。推理小説研究会の会長江神二郎と有栖は、恐怖と疑心暗鬼に陥る学生とともに噴火の中に取り残された危機的状況を乗り越えつつ、事件の真相に迫って行く。
有栖川有栖のデビュー作である英都大学の有栖川有栖&江神二郎コンビ3部作の第1作である。設定の不条理感は、Yの悲劇というよりはシャム双子の謎に近く、そういう小説ではないとは思うが、噴火による危機感がどうも伝わってこないが、それはそれで、不条理感の醸成につながっているともいえなくはない。
(★★ 1996)
孤島パズル/有栖川有栖/創元推理文庫
英都大学推理小説研究会の新入部員有馬麻里亜に招かれ、アリスと江神は孤島の別荘でマリアの親族と共に真夏のバカンスを過ごすことになった。島にはパズルに隠された財宝があり、二人はこのパズルを解くために訪れたのだった。事件は台風が接近した夜に起こり、滞在客の2人が殺害される。本土との連絡手段が絶たれた孤島で更に殺人事件が発生する。江神二郎はパズルを解くとともに、事件の真相を究明する。
アリス&江神コンビ3部作の第2作。前半でアリスとマリアの物語が淡く叙情的に語られている点は青春小説として高く評価できる上に、このロマンチックなエピソードが後段で事件解明の鍵となるべく巧妙に溶けこまされている。江神の推理の論理展開もきれいに決まっており、本格推理小説としても、前作を上回る傑作であるといえる。
(★★★ 1996)
双頭の悪魔/有栖川 有栖/創元推理文庫
前作「孤島パズル」事件の心労からマリアが、四国の山間の過疎地で孤立する芸術家のコミュニテイ木更村に入ったまま帰らない。英都大学推理小説研究会一向は、心配する両親の依頼で彼女を説得するために河を一つ隔てた対岸の夏森村に到着するが、木更村の住民からかたくなに接触を拒まれてしまう。大雨の中、村への潜入を試み、江神一人のみが成功する。しかし、暴風雨で木更村は連絡が途絶し、しかも両方の村で、それぞれ殺人事件が起こり、江神、マリア、アリスによる真相究明が開始される。
あいかわらずの不条理な舞台設定で、殺人事件に現実感が希薄であるが、これこそがこの3部作の持ち味である。意図されたものかどうかは不明であるが、こうした夢の中の出来事のような現実とのずれが、主人公たちの空回りする感情だけを逆に奇妙なリアリティをもって浮彫りにしている。この構造こそが若く未熟な青春の思い出そのものなわけで、本3部作をノスタルジックな青春小説たらしめているものといえよう。
(★ 1998)
46番目の密室/有栖川有栖/講談社文庫
推理作家有栖川有栖と臨床犯罪学者火村英生は、密室物の権威とされる推理作家真壁聖一邸でのクリスマスパーテイに参加していた。このパーティには、真壁の家族のほか推理作家、編集者などが招かれていたが、パーティが終わる頃、彼らの滞在する部屋には不思議ないたずらが施されていた。その夜、有栖が邸の異変に気付き、見まわりに出たところ、鈍器で殴られ気を失ってしまう。その後、見知らぬ男と真壁が死体で発見され、有栖と火村は捜査に乗り出す。
アリス&江神コンビ3部作と比べると本格ミステリー度は高まっているのだろうか。トリックに拘り、探偵役火村の推理も悪くない。しかし、クローズドサークルとノスタルジーが絶妙なハーモニーを醸し出していた前作と比べてしまうと、どうも何かひとつが足りないような気がしてしまう。本格ミステリーといえども、探偵とトリックと論理展開だけで成り立っているのではないことを感じざるを得ない。最後は好みの問題であるのかもしれないが、そうだとしても、私は本作より前の3部作に1票いれてしまいそうである。
(★)
スウェーデン館の謎/有栖川有栖/講談社文庫
一人で雪深い裏磐梯を訪れたアリスは、勘違いから北欧系の美人ヴェロニカと知り合う。童話作家を夫に持つ彼女にスウェーデン館と呼ばれるログハウスに招待されたが、そこで殺人事件の悲劇に巻き込まれる。真相にたどり着けないアリスは臨床犯罪学者火村に捜査を依頼する。
有栖・火村コンビの2作目の長編だが、本作は、どこか成熟しきれていないアリスによる学生アリス3部作的な目線で物語が描かれており、これが今回のストーリーとうまくあっていように見える。本格物としてのトリックや小道具の処理のし方は、いつもどおりの手練れである。
(★)
亜愛一郎の狼狽/泡坂妻夫/創元推理文庫
頼りなげだが本質をはずさないカメラマン助手の亜愛一郎の活躍を描く著者のデビュー短編集。
地方の名士柴が搭乗する爆破予告を受けたDL2号機が無事に着陸する。彼は好んで何かいわくのあった土地や人を求めているようだが、とうとう彼の屋敷で殺人事件が発生する「DL2号機事件」、宣伝用の熱気球の中でたった一人で乗っていたはずの芸人が銃殺される「右腕山上空」、マンションの鏡像関係にある二つの部屋を舞台に発生する殺人事件「曲がった部屋」、ホテルに向き合って立つ巨大な観音像の上から仮面をつけてチラシをまいていた男が銃で撃たれて死ぬ「掌上の黄金仮面」、強盗に襲われたタクシー運転手の車から強盗犯人の死体が発見される「G線上のいたち」、全文ひらがな童話の童話に隠された秘密「掘り出された童話」、戦時中、ホロボ島で日本兵と現地の少数民族の間で発生した事件を描く「ホロボの神」、事故で散布されたカーボンで黒い霧に包まれた街で起こった事件「黒い霧」。
トリッキーな名作ぞろいの短編集。特に、視点や発想が独創的で、ストーリーの構成力も確かな短編群である。その中では、正統派のトリック崩しでは「曲がった部屋」、独特の発想という点では「DL2号機事件」、ホームズ物のようで楽しい暗号小説「掘り出された童話」といろいろあるが、私は味わい的には「G線上のいたち」を一押ししたい。
(★★ 1997)
亜愛一郎の転倒/泡坂妻夫/創元推理文庫
ちょっと変わっているが、観察眼が鋭く、謎の真相をみぬいてしまう亜愛一郎の活躍を描く短編集第2弾。
亜愛一郎は、写実主義の画家・粥谷東巨の回顧展で、作品を見ていると、絵の中になど、現実ではあり得ない奇妙なもの(6本指、開かない扉、間違っている時計の針、物理法則を無視した水差し等々)が描かれていること気付く「藁の猫」
列車が土砂崩れで不通となり、徒歩で先を急ぐこととした亜愛一郎はたどり着いた民家で一夜を明かすが、翌朝、隣家の合掌造りの家が消失してしまう「砂蛾家の消失」
飛行機事故で亡くなった歌手・加茂珠洲子の人気が死後急上昇し、彼女の生涯を描く追悼映画を作るために、オーディションが開かれる「珠洲子の装い」
山奥の温泉地で発見された変死体は、有名な童謡のとおりに、鉄砲で撃たれ煮られ焼かれて木の葉で隠されていた「意外な遺骸」
亜愛一郎と大竹教授が偶然帽子を拾うが、その持ち主は怪しい雰囲気を漂わせている「ねじれた帽子」
引退した地元の大物4人が人を寄せ付けず離れに閉じこもる。彼らは何をしているのか「あらそう四巨頭」
タクシーの中に突然現れた一度おろしたはずの客の死体。その直前に亜愛一郎らが乗っていたことから事件に巻き込まれる「三郎町路上」
出版社の友人を見舞いに来た亜愛一郎だが、この友人の病院で同室だった患者が病院の屋上で殺害される「病人に刃物」
「ブラウン神父シリーズ」なみの名作連発の短編集。クイーンをはじめ建物の前例はいろいろある中で野心的な挑戦を見せる「砂蛾家の消失」、 葉を隠すなら森の中的な要素が決め手の童謡見立て殺人の「意外な遺骸」、意外な結末を見せる「三郎町路上」と「病人に刃物」とあるが、一押しするのは、ダイイングメッセージ(とは違うが)とホワイダニットが融合したような傑作「藁の猫」である。
(★★)
亜愛一郎の逃亡/泡坂妻夫/創元推理文庫
謎の名探偵の亜愛一郎がその正体を現し、我々の前から姿を消してしまう3部作の完結編。
裸体主義者達が赤島という無人島で全て裸で電気もガスもない生活を送っていた。そこに、モーターボートに乗った服を着た男が現れ、騒動が起こる「赤島砂上」
極端な人間嫌いの大富豪が、究極の災害シェルターである球形カプセルの密室状態の中で死体で発見される「球形の楽園」
刑事の井伊和行は10年前に治療した歯が痛み歯医者へ。そこで、奇妙な行動をとる上岡という男をみかける「歯痛の思い出」
週刊誌の記者・亀沢均は、双頭の大蛸を見たという小学生のはがきに基づき、取材をしに北海道へ。そこで、湖を調査中にダイバーがボート上で殺害されてしまう「双頭の蛸」
亜愛一郎ら一向は化石の調査に狭隘な山道へ行く。そこを何台も車が通るが、その中の1台が谷底に転落する。それは事故ではなく他殺であった「飯鉢山山腹」
曙光展の華々しい開幕式。しかし美術評論家・阿佐玲子は、鏑鬼正一郎の赤を基調とする画風が変化し、鮮烈さを失ってしまっていたことに失望していた。鏑鬼正一郎の過去から亜愛一郎が変化の理由を解き明かす「赤の讃歌」
火事が大好きで消火活動を手伝う酒屋の主人・銀蔵に、放火・殺人の嫌疑がかけられる「火事酒屋」
雪に覆われた宿の離れにいたはずの愛一郎とその連れは、忽然と姿が消えうせていた。ついに亜愛一郎の招待が明かされる「亜愛一郎の逃亡」
3作目になってもクオリティが下がることのない短編集。芸術家の過去を鮮やかに描き出してみせる「赤の讃歌」や伏線がよく効いている「火事酒屋」もよいが、一つだけ選ぶとすれば、ケメルマンの「九マイルでは遠すぎる」のようなアクロバティックな推理が展開される「歯痛の思い出」に落ち着く。
(★★)
オーデュボンの祈り/伊坂幸太郎/新潮文庫
ささいな事情からプログラマをやめて失業中の伊藤は、コンビニ強盗を行ない、古い知り合いの悪徳警官に逮捕されるが、逃亡を企てる。朝、気がつくと、彼は、誰も知らない小島へと連れてこられていた。その不思議な島では、口をきくことができすべてを見通すカカシ、人を殺すことを認められた男、嘘しかつかない男、太りすぎて動けなくなった女、死にいく者の手を握ることを職業とする女など風変わりな人々が、風変わりなしきたりで暮らしていた。そんな中でカカシが殺されてしまう。誰がこの島の人々に敬愛されていたカカシを殺してしまったのか。
小説は何でもできるのだ。そして、その中の手法的分類であるミステリーでも。設定がはまった瞬間にこの小説は小説として成立したといえよう。伏線がよく効いているという話を聞くが、伏線のおき方はそれほど巧みとはいえないし、それが結実した効果も大きくは驚かせてはくれない。それはやはり、あらかじめ伏線がすごいよと知ってしまったからなのだろう。残念。
ところで、「逃げる」主人公・伊藤は一体どう変わったのだろうか。コンビニ強盗をして人生をリセットしようとした彼、幼い頃から自分の手に負えない悪漢城山を結局、桜の手によって消し去った彼は、一体どのように成長したのだろうか。彼女の静香はこのおかしな経験を通して変わったかもしれない(少なくとも変わるチャンスはあった)のに、私たちの世の中の映し鏡ともいうべき荻島の奇妙な生活で何を得たのだろうか。別にミステリーなのだからそんなことどうでもよいのかもしれない。誰もシャーロックホームズやエラリークイーンの成長譚など彼らの小説に求めていないのだから。しかし、本作のもったいぶった人生に対する警句の数々は、では何のためにあったのだろうか。これらは何かの伏線ではなかったのか。そう、伏線がすばらしいという評価に対して素直にうなづけないのはそうしたことも理由になっているのかもしれない。
ところで、カカシが考え、話す原理が秀逸。
(★★ 2005/01)
陽気なギャングが地球を回す/伊坂幸太郎/祥伝社NON NOVEL
他人の嘘を見抜き、物事の先を読むことができる成瀬を中心に、演説とでまかせの天才響野、人より動物を愛する少年のようなスリの達人久遠、正確な体内時計を持つ雪子の4人はチームで一度も失敗することなく銀行強盗を行ってきた。今回のターゲットは港洋銀行だが、しきりと中学生の息子を心配するなど雪子のようすがおかしい。そして、銀行強盗を決行するが、いつも通り現金を奪取し雪子の運転する盗難車で逃走している途中、別の現金輸送車ジャックの一味と接触事故を起こし、奪った現金を横取りされてしまう。彼らは、久遠が掏り取った携帯電話から犯人グループを探っていく。
ストーリーとしては、クライムノベルお約束の最後のどんでん返しがきちんとなされている。くるぞくるぞという場面でのクライマックスで、いくつかの伏線がきちんと収束している。はずしてきそうなキャラクターと展開だったので直球で来た分、逆にすこし肩すかしであったかもしれない。不思議な読後感。誰にも感情移入させないように構成されていて、リアルな感じがしないように感じる。では、寓話的かというとそういうわけでもなく(寓話性を著者はあとがきで否定している)、もちろん重く残るものもない。
ストーリーのメインストリームと離れたところに、弱くても他人から評価されなくても懸命に生きている人々が、整理されることもなく描かれているのが印象的。この脇役たちの問題は深く掘り下げられることなく放り出されていることで現実味を帯びており(世の中では、それぞれの人にとって他人の問題は常に放り出されたままだ)、それが主要キャラクタたちの厚みのために奉仕している。このあたりの考え込ませないところなどは、エンターテインメントとして潔い。
(★ 2005/03)
忠臣蔵 元禄十五年の反逆/井沢 元彦/新潮文庫
忠臣蔵をテーマにした芝居を書くことになった小説家の道家和彦が謎の妨害を受けつつ、真実の忠臣蔵を追究していく。本作の大部分は、「仮名手本忠臣蔵」の真のメッセージの解明(将軍綱吉の存在)と「忠臣蔵」の存在によって真実が見えなくなってしまった「赤穂事件」の実相(事件の最重要人物・浅野内匠頭とはどんな人物であったのか)を明らかにすることに費やされる(そもそもキャラクタにしたところで、従来の学説を主張する大学助教授が新しい説を補強するために最初から打ち砕かれる反論を唱えるだけの存在であるように、すべてそのためだけに造形されたもの)。
小説としての完成度を議論するような類のものではないと思われる。忠臣蔵(正しくは赤穂事件)という歴史的事件の解明が圧倒的にスリリングで、読みどころもこれに尽きているからである。既存の学説で固まっている歴史学者を論破するところは、名探偵が一同を集めて自らの推理を披露し、犯人を指摘するどんな場面より、カタルシスがあるといってもよい。これを読んでしまうと、毎年のように年末に流される同工異曲の忠臣蔵は、空々しくて見られなくなってしまうのが困った点である。
(★★★★)
信用調査マン日誌―プロが教える情報収集術と企業分析法/石倉潔/日経BP社
長年信用調査会社で企業の調査を行ってきた著者が、どのように企業情報を得て、その情報から何を読み取るのかということをまとめたものである。倒産の舞台裏で何が起こっているのか、粉飾決算の手口や企業の幹部の遊行、背伸びをした経営等の実例を通して、危ない会社の兆候は何か等が、生々しく語られている。また、相続の悲劇の章を見ると企業経営が人間の弱さと密接に絡み合っているものであることが切実に伝わってくる。
私は、金融機関のはしくれで働いているものの、この真の意味での現場である最前線での人間臭いドラマを必ずしも完全に理解していたわけではなく、この中で紹介されている著者の実体験に基づく事例の一つ一つが興味深く、身にしみるものであった。ある特はお人よしが、ある時は一時の成功者が、ある時は真面目人間が、またある時は子供を愛するものが、経営を失敗して行くさまは、企業経営というぎりぎりのところで人の弱さがさらけ出されていく様子そのもので、戦国大名の興亡の物語と変わるところがない。場合によっては、「プロジェクトX」や「ガイアの夜明け」などよりよほどビジネスマンに世間の風を理解させる書かもしれない。
(★★ 2004)
長い家の殺人/歌野晶午/講談社文庫
大学生ロック・バンド「メイプル・リーフ」のメンバーは、最後のライブのための合宿で越後湯沢のロッジ「ゲミニー・ハウス」を訪れる。合宿初日の夜、メンバーの一人戸越が自分の部屋からと姿を消し、翌日、戸越は自室で絞殺体で発見される。事件は解決されないままライブの日を迎えるが、ライブ会場楽屋でメンバーの一人が、絞殺される。このバンドのかつてのメンバー信濃譲二が事件の捜査に乗りだす。
トリック一発ものの宿命として、ミステリー読みにはおちが見えてしまうのだろうし、だから評価が低いという向きもあるかとも思う。しかし、この種のミステリーはトリックの発想を楽しむべきもので、それが読者に見抜けるかどうかなどということはその作品の評価とはあまり関係ない(そうじゃなければ『占星術殺人事件』の評価などどうなってしまうのだろう)。ただ、とはいえ、この小説としてのできばえはまだトリックを生かすだけの文章力が伴なっていないために、いま一つといわざるを得ないのも事実。
(★ 2001)
情報と国家―収集・分析・評価の落とし穴/江畑謙介/講談社現代新書
情報収集についての手法の紹介に始まり、公刊情報の持つ価値、インターネット、エシェロン、衛星写真、そして人的ソースによる情報(HUMINT)まで、その収集方法による情報の特徴が説明され、情報収集とは如何なる作業をすることなのかを明らかにする。次に情報の分析の核心が、イラク戦争をめぐる米国・イラク等の情報分析を例に解説される。最後に他国からもたらされたような情報をどのように評価していくのか、北朝鮮をめぐる情報をどのように評価すべきであったのか詳しく論じられる。
まさにタイトル通り国家戦略上必要不可欠な行為である情報の取り扱いについて論じた書である。軍事オタク的要素を取り上げる局面はほとんどなく、きわめて冷静に情報戦を分析しており、著者の容貌からうける印象とは異なる確かな議論の積み重ねで構成されている良書である。特に感銘を受けるのは、インテリジェンスとはその状況における最良の推測であればよく、真実である必要はないというくだり(マイヤー統合参謀本部議長の発言の引用)である。これは冷徹な現実を言い表している。しかし、最良の推測であるべく努力する必要があり、真実でなくてもよいというところに逃げてはいけない。
また、情報の評価は、常識と専門知識を駆使せよという部分も、仕事上の判断で迷ったら最後は常識に頼るべきであると私も常々考えていたため、インプレッシブであった。イラク戦争時に、結論ありきで上司の気に入るような情報を挙げてくる部下の姿勢について記されていたが、いずこも同じ宮仕え、その心情はよくわかるよと妙なところで感心。
(★★★ 2005/01)
金融アンバンドリング戦略/大垣尚司/日本経済新聞社
80年代以降米国では金融技術が劇的に進展し、90年代以降それに伴ってビジネスモデルを変革させていったのに対し、日本の金融セクターは、米国発の金融技術革命には対応してきたものの、その技術を活かすための経営方法を変革させることはできずにいた。本書は、こうした金融界の新しい経営の枠組・ビジネスモデルを提案するものである。その考え方のコアにあるものは、業態縦割り型の現在の構造を変えて、重複した経営資源を効率化することを前提に、機能ごとにセクター構造を見直し、オリジネーション、サービシング、マニュファクチャリング、リスク管理、資金調達といったブロックごとにアンバンドリングを行っていくことが重要であると説かれている。
軸のぶれない骨太の金融セクター改革の書である。わが国の製造業が日々技術の革新を行っていくとともにそれを活かすための経営のあり方を不断に模索しているのに対して、明らかに金融の経営は遅れている。私も金融セクターのはしくれに身を置く者としてそれは痛感する。本書の中でも冷静に批判されているように、規制緩和に抵抗する民のプレイヤーの改革へのブレーキが常にあり、このままでは金融セクターは緩慢な死を迎えることになりかねない。
マイナス財としての金融商品の特徴、管理型信託会社を活用した新ビジネス、プロジェクトマネジメントの重要性、勝負の決まっていない合併の不安定性やビジネスモデルの変革なき公的金融機関の民営化のリスクなど、どこをとっても知的アピタイトを満たす書であった。
(★★★★ 2005/02)
新宿鮫/大沢在昌/光文社文庫
新宿暑の鮫島警部は、公安内部の暗闘の中で自殺した同期の警官から託された手紙を恐れる警察上層部によって、新宿署防犯課に一介の刑事として塩漬けにされていた。そんな事情から誰も彼と関係を持ちたがらず、彼は常に単独で行動する刑事であった。ある日、歌舞伎街で連続して警官がライフルで射殺される事件が発生する。鮫島は、銃の密造屋木津をマークする。
大沢在昌が大きく飛躍することとなったハードボイルドの佳作。自分の属する組織の矛盾に苦しみ、組織に対するアンビバレントな気持ちを抱く組織人というのは、多くの人々の共感を得られやすい設定かもしれない。特に、みんなそんなにかっこよくはないけれど、本人の指向が組織の建前と一致しているような場合においては、同じようなものを抱えているのである。ストーリーは、ハリウッド映画のように単純明快。そういえば、ハリウッドではなかったが、映画化されたんだった。
(×)
捕手論/織田淳太郎/光文社新書
最近、戦う選手会長古田をはじめ明るいキャラクタの選手が現れスポットライトが浴びる機会が多くなってきた裏方ポジションのキャッチャーをとりあげたスポーツルポ。古田のリードの特徴、捕手から見た江夏の21球、投手や審判との関係やチームの中での役割、メジャーの捕手との違い、それにおまけの読売V9捕手のMの陰湿エピソードなど盛りだくさん。期待していた捕手のリードについての掘り下げが弱く、「捕手論」というにはやや寂しい内容ではないか。軽い読み物として、プロ野球選手のエピソードを読むにはいいかもしれないが。
(×)
秘密結社―アメリカのエリート結社と陰謀史観の相克/越智道雄・ビジネス社
本書は秘密結社による世界支配を面白おかしく描いた「ト」本の類ではない。アメリカ合衆国の建国から説き起こし、同国の支配層たるエリートのネットワーク を「秘密結社」としている。フリーメースン、スカルスアンドボーンズ、ミルナーグループ、日米欧3極委員会などを丁寧に解説し、これらが米国の政治にどの ような影響を及ぼしているかが説明される。そして「結社」のカウンター勢力として「陰謀史観」を位置づけていて(陰謀史観については、本質的な歴史の見方として因果律を逆転させているとして批判を加えている。)、巧みに「秘密結社=陰謀」という先入観を 崩しつつその関係を再構成して見せてくれている。
本書は、時にオカルト的に語られる秘密結社が、私達がふだん見ている2大政党という表面的なポリティカルパーティを直接間接支える人的ネットワークととらえてみせた、非常によくできた米国政治の解説である。 公明正大なルールで運営されている民主主義の国・米国でも、ある面では、ラテンアメリカ諸国の政治に近いような濃密な人のつながりなしには政治は動かないということが見えてくる。政治の本質はどこまでいっても、人の欲望や情念の産物であるからということか。
米国に限らず、この世界の真の支配者層のネットワークというのは、極めて排他的かつしたたかに作り上げられていて、そこに属さない人々の無力ぶ りを痛感させられる。そうした世界や社会のありようを前提として、私たちは何を追及して生きていくのかは、個々人がよく考えなければいけない ことである。
タブーを犯すことが秘密結社にはいるための儀式となっているということは、リーダーシップが本質的に内包している矛盾そのものを表しているという部分は、まさに何らかの組織に属する構成員ならうなづける部分であろう。著者が説くように、現代人はこれに対して「市民」として糾弾する立場も有している。さしづめ、ワイドショーを観るサラリーマンという絵図か。
米国(あるいは英国)では、時代にふさわしい秘密結社が登場するという。特に現代のような衰退期には、政権の中枢へ頭脳を送り込むような結社が現われ、それがネオコンだとするのもなかなか穿った見方ではある。こうした米国の対応速度の速さは、自由や民主主義という燃焼速度の速い観念群を掲げているためであり、暴走しがちであるというのも、わかりやすい。その意味では、旧ソ連と米国は極めて似た構造にあったといっても過言ではないのではないか。
本書の最後の方で出てくるブッシュ政権を支えるキリスト教右派の位置づけをきれいに見せてくれている点(真実かどうかはともかく)が目からうろこであった。 確かに、民衆とエリートとの間で、つまり選挙と国政運営というまったく異質な手順の間で綱渡りを強いられることこそがアメリカ政治の要諦であるというのは、その通りである。
「正しい世論は主として、事実と本当に接触できる、関連問題を考え抜いた少数の人々によって生み出されるものだ」(ライオネル・カーティス)
(2005/12 ★★)
七つの棺―密室殺人が多すぎる/折原一/創元推理文庫
折原一らしい密室もののマニアックなパロディのみを推集めた短編集。どの作品も初めに提示される謎は大きく、それをはぐらかすようなちょっと間抜けな解決を見せている。この中では、「ディクスン・カーを読んだ男たち」、「懐かしい密室」と「不透明な密室」がかなり力が抜ける。
(×)
| SEO | [PR] おまとめローン 花 冷え性対策 坂本龍馬 | 動画掲示板 レンタルサーバー SEO | |
