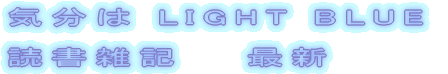
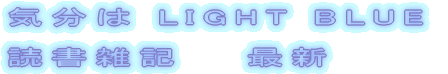
秘密結社―アメリカのエリート結社と陰謀史観の相克/越智道雄・ビジネス社
本書は秘密結社による世界支配を面白おかしく描いた「ト」本の類ではない。アメリカ合衆国の建国から説き起こし、同国の支配層たるエリートのネットワーク を「秘密結社」としている。フリーメースン、スカルスアンドボーンズ、ミルナーグループ、日米欧3極委員会などを丁寧に解説し、これらが米国の政治にどの ような影響を及ぼしているかが説明される。そして「結社」のカウンター勢力として「陰謀史観」を位置づけていて(陰謀史観については、本質的な歴史の見方として因果律を逆転させているとして批判を加えている。)、巧みに「秘密結社=陰謀」という先入観を 崩しつつその関係を再構成して見せてくれている。
本書は、時にオカルト的に語られる秘密結社が、私達がふだん見ている2大政党という表面的なポリティカルパーティを直接間接支える人的ネットワークととらえてみせた、非常によくできた米国政治の解説である。 公明正大なルールで運営されている民主主義の国・米国でも、ある面では、ラテンアメリカ諸国の政治に近いような濃密な人のつながりなしには政治は動かないということが見えてくる。政治の本質はどこまでいっても、人の欲望や情念の産物であるからということか。
米国に限らず、この世界の真の支配者層のネットワークというのは、極めて排他的かつしたたかに作り上げられていて、そこに属さない人々の無力ぶ りを痛感させられる。そうした世界や社会のありようを前提として、私たちは何を追及して生きていくのかは、個々人がよく考えなければいけない ことである。
タブーを犯すことが秘密結社にはいるための儀式となっているということは、リーダーシップが本質的に内包している矛盾そのものを表しているという部分は、まさに何らかの組織に属する構成員ならうなづける部分であろう。著者が説くように、現代人はこれに対して「市民」として糾弾する立場も有している。さしづめ、ワイドショーを観るサラリーマンという絵図か。
米国(あるいは英国)では、時代にふさわしい秘密結社が登場するという。特に現代のような衰退期には、政権の中枢へ頭脳を送り込むような結社が現われ、それがネオコンだとするのもなかなか穿った見方ではある。こうした米国の対応速度の速さは、自由や民主主義という燃焼速度の速い観念群を掲げているためであり、暴走しがちであるというのも、わかりやすい。その意味では、旧ソ連と米国は極めて似た構造にあったといっても過言ではないのではないか。
本書の最後の方で出てくるブッシュ政権を支えるキリスト教右派の位置づけをきれいに見せてくれている点(真実かどうかはともかく)が目からうろこであった。 確かに、民衆とエリートとの間で、つまり選挙と国政運営というまったく異質な手順の間で綱渡りを強いられることこそがアメリカ政治の要諦であるというのは、その通りである。
「正しい世論は主として、事実と本当に接触できる、関連問題を考え抜いた少数の人々によって生み出されるものだ」(ライオネル・カーティス)
(2005/12 ★★)
ジャパン・ハンドラーズ―日本を操るアメリカの政治家・官僚・知識人たち/中田安彦/日本文芸社
米国の対日戦略を練り上げ、実行する人々のネットワークを調べあげてまとめたもの。大学・シンクタンクの研究者の系譜を中心に米国側の対日戦略 を仕掛ける側とそれを受け日本側で動くカウンターパーツが実名入りで紹介されていく。どのように日本が米国に取り扱われてきたかが浮き彫りになる。
正直、最初この本を本屋で見たときには、巷間出回っている「○○陰謀論」の類の胡散臭さを感じた(それは今も完全に払拭されたわけではないが)。しかし、冒頭に出てくる日米コネクション相関図を見て買うことにした。これはなかなかよく出来たチャートで、私は仕事柄、ここに出てく る人物のひとりに関する話を知っているが、そこを全貌ではないにせよ抑えているので、それなりにちゃんと調べたのかなと思ったからである。
内容は、日米関係者の両国関係の基本を作り出しているキーマンの人物名鑑になっていて、今後の日米関係の動きに接していく時に、背景が見通しやすくなりそうなまとめられ方がされていてお役立ち度が高そう。論調は、取り上げた人々の発言や著作物の引用をたくみに組み立て、ファクツを積み上げる形式をとっており、妙な誘導や冒頭にあげたような陰謀論などはなく、新聞を読むように読めてしまう。
簡単に読めてしまうのは、ここに書かれたことの大部分がそれほど目新しいことではないことに由来している。米国の対外戦略において「どのよう に」の部分は、陳腐な印象が強く、この本の肝は、「誰が」という部分にあるのでいたしかたないとは思うものの、そこは掘り下げがもっと あってもよかったのではないだろうか。 それと、本書のターゲットではないが経済界での動きは、個人的にもっと興味がある分野でもあり、今後さらに調査を進めて発表してもらいたい。
(2005/06 ★★)
幻の終わり/キース・ピータースン/創元推理文庫
硬派の新聞記者ジョン・ウェルズは、ある晩著名な戦場ジャーナリスト・ティモシー・コルトと出会い、意気投合する。しかし、彼のホテルの部屋で酔いつぶれ ているとジョンの目の前で謎の闖入者によってコルトは殺されてしまう。手がかりは彼がアフリカの小国セントゥーで活躍していた過去とその時彼が愛したエレ ノアという名の女性だけ。ジョン・ウェルズは、その後も命をつけ狙われながら、徐々に真相に迫っていく。
主人公ジョン・ウェルズのキャラクターは世間で紹介されているほど屈折した中年ではなく、どちらかといえば、頑固で思い込みが強く、そう したことで対立してしまう自分に対する憐憫を持っているタイプで、つまり、多かれ少なかれ中年になると現れてくる現象に満ち溢れた男。本作では、彼の弱い内面と虚勢を張る外面のギャップをドライに過ぎないように描いて見せている。
しかし、本作のドライビング・フォースとなっているキャラクタはやはりエレノアということになるのだろう。ウェルズにとっては伝聞でしか出てこないこの女性を如何にリアルに描くかが本作の肝であるといっても過言ではない。そう考えてみると、ちょっと肝心なところで食い足りない印象が残ってしまう。コルトが彼女を愛するのはわかるが、どうしてウェルズま で夢中になってしまうのかが、決定的に弱い。革命前夜の途上国で活躍したジャンヌダルクのようなエレノアは、説明はされていますが、描写はされ ていません。それが弱さの原因であろう。
終盤に来てウェルズの恋人チャンドラ・バークとの関係に絡めてウェルズの物語にしようとはしているが、エレノアの弱さゆえ、全体に説得力が減じられている。
(2005/06 ★)
古い骨/アーロン・エルキンズ/ハヤカワ文庫ミステリアスプレス
フランスはモン・サン・ミシェル近くにあるロシュボン館に主の招待で一族が一堂に会する。主、ギヨーム・デュ・ロシェは招待した一族に重大な何 かを告げようとする直前に、モン・サン・ミシェル湾で事故死してしまう。さらに館の地下からは古い人骨が発見され、偶然サン・マロで開催されていた科学捜 査会議に出席していたスケルトン探偵のギデオン・オリヴァーが骨の分析のため呼ばれる。一族の残る館では殺人事件が発生し、問題の核心は第2次大戦のレジ スタンス活動家であったギヨームとそのいとこのアランの過去であることが判明していく。
軽いタッチの本格物小品(という分野があるか知らないが)で、真相はそこそこ重い話にし得たのだろうが、さらっと流されてある。第2次大戦中のレジスタンス活動なんて刺身のつまだと軽く扱って見せるところがいかにも本格推理物というところだろうか。
骨の鑑定から事実の確認へという流れで捜査を進めていくギデオンの探偵スタイルは、現代の本格推理小説としてリアリティを崩さず、パズラーとしての本筋もはずさずよく出来ている。 謎の中心部はミステリー読みには意外ではありませんが、犯人の指摘がなされる解決部は、本格物ならではの関係者一同への演説となっていて、楽しい。
キャラクターはちょっとカリカチュアライズされているが、ユーモアたっぷりに描かれていて(特にギデオンの許に手紙爆弾が届けられたのではないかと考えるギデオンとジョン・ロウのやりとり)、ステレオタイプ 化されることなく踏みとどまっている。
(2005/05 ★)
エリー・クラインの収穫/ミッチェル・スミス/新潮文庫
ニューヨーク市警遊軍部隊の女性刑事エリー・クラインは能力はあり手柄をたてることもあったが、警官としての適性については疑問しされていた。彼女とその相棒トミー・ナードンは、高級娼婦が自宅のバスルームで殺害された事件を追うこととなる。
これでもかというほど微に入り細にわたりエリーの日々がつづられていく。そこで明らかにされるのは娼婦サリー・ゲイサー殺人事件の真相だけ ではなく、警察機構の中での遊軍部隊の微妙な役回り、娼婦の娘への告白、レズビアンの関係にある恋人との生活とすれ違い、性転換をし不治の病に冒された重 要証人との交流やストーリー上まったく関係のないキャラクターとの接触などなどエリーにかかるあらゆることであるといっても過言ではない。彼女が描 く絵のことや妄想までもが綴られていく中で、エリーという人物にリアリティがでてくるということなのだろうか、中途半端なドラマがなく、ひたすら人物の存 在感を出すべく描きこみがなされている。
ただ、その割にリアルな印象が弱いのは、読み手の想像力を奪ってしまうような大量の描写があるからではないかとみえる。あるいは、人物のど うでもよい日常に立ち入りすぎてちょっと辟易してしまうのかもしれない。しかも、本筋はちょっと弱いプロットになっていて、分厚い描写でエリーへ向かっ た感情移入が頼りなげなストーリーのために支えきれいていないように感じられる。
不思議なもので、描きこみが足りない相棒のトニー・ナードンが少しステレオタイプなものの一番魅力的な存在感をもっている。つくづく小 説の描写のバランスは難しいものだと思う(もちろんそれにあらゆる読み手を満足するような描写の水準というものはないのかもしれない)。
ところで、まったく本書の価値とは関係ないのですが、新潮文庫は活字の大きさ濃さや配置のせいか、どうも読みにくい。
(★ 2005/05)
大人の男のこだわり野遊び術/本山賢司、細田充、真木隆/山と渓谷社
この本を近所の小さな図書館から借りて読むのも、今回で3回目。
アウトドアの達人によるキャンプマニュアルのような本とはまったく異なる趣の本である。その大部分は、道具の話に費やされ、それも手に入れやすさ(少なくとも街のアウトドアショップでは)とか、手軽さ(便利でない、ということは意味しない。むしろその正反対)とはまったく無縁のものを紹介している。本当の使いやすさをフィールドの経験から説く。そして、本書の読みどころの焚き火にまつわる蘊蓄。
たぶん、ずばりそうは書いていないが、世の中のオートキャンプ場に集う人々の行動が気に障るのであろう。それは、そうした「なんちゃってアウトドア」派が素人だからではなく、自然のフィールドの中での振る舞い方をわきまえていないからに相違ない。この書が伝えるのは、アウトドアに飛び出す者は、己を知り、分をわきまえ、自然の中で謙虚にしかも真剣に遊ぶべしというメッセージである。
グッズに関しても、メーカーの与えるモノを盲信するのではなく、自分の頭で考えよということだと思い、いろいろともっとよいものを考えて行動するようにしているが、寝袋だけはけちってはいけない。それと、「なんちゃってアウトドア」派なので、ものすごく簡単に設営できるタープをついに買ってしまった(これも堕落か)。とはいえ、この本の書きぶりには、スノビズムが相当紛れ込んでいるのも、否定できない。
(★★ 2005/05)
裁くのは誰か?/ビル・ブロンジーニ&バリイ・N・マルツバーグ/創元推理文庫
合衆国大統領のニコラス・オーガスティンは、任期の最後の半年で外交・内政に関する失言で支持率を落とし、党内でも二期目は別の候補者でいこうとする動きが出ている。彼はそうした世論やマスコミ、党の流れに抵抗しつづけている。やがて、大統領の側近たちが裏切り行為を行っていると考える何者かが「慈悲の行為」として彼らの暗殺を開始する。
米国の大統領をとりまく事象とそこで起こる連続殺人ということであれば、結末はどうであれ、もう少し描き込みが必要なので(特に米国の小説であれば、これ見よがしにデータが羅列されるのが普通。日本のだと、そういう種類の小説でもこのくらいの情報量でも平気なんだろうけど)、地の文の方でなんか妙だなと思う。
しかし、権威に負けたというわけでもないが(?)、まさか大統領まで引っ張り出してきてこのトリックはないと思いこんでしまう陥穽をつかれる。設定や舞台とのギャップでこのトリックをうまく見せたということか。凡庸だとは決して思わないが、驚天動地の結末というには遠いのでは。
(★ 2005/04)
深夜プラス1/ギャビン・ライアル/ハヤカワ文庫
主人公のルイス・ケインは元英国諜報部員で対戦中にはフランスでレジスタンス活動に身を投じていた闘士である。彼が引き受けた仕事が、婦女暴行犯の疑いをかけられフランス警察にも追われる身である実業家マガンハルトとその秘書を車で密かにブルターニュからリヒテンシュタインへ無事に連れて行き、投資先会社の株主総会に出席させることにあった。ケインの相棒のガンマンはアルコール中毒のハーヴェイ・ロベルとフランス警察を出し抜き、姿の見えない敵の攻撃をかいくぐり、制限時間内にリヒテンシュタインを目指す。
現代読んでもまったく色あせていない冒険小説である。入念に構成されていて、全体の整合性を乱すような要素がまったく混じらない。キャラクターは少々ステレオタイプな所もあるが、生き生きとして、その会話も緩んだところがない。個々の場面は、すべてこの4人だけのシーンでつながれていく。回想シーンもなければカットバックもない。驚くほどストイックな構成といえよう。近年の小説群のように長すぎることもなく、過不足なくまとめきられている。確かに名作の名を恣にするだけのことはある。
あまりほめてばかりいても芸がないので、ちょっと気になったところを一つだけ触れると、最後にケインがちょっと得意げに真相を語ってみせる所があって、これは瑕疵とまではいえないが、どうもそれまでのストイックさがなく説明調になっているように感じられる点である。
とにかく、冒険小説の教科書のような小説である。
(★★★ 2005/04)
ホワイトハウスの記憶速読術/齋藤英治/ふたばらいふ新書
本書はピーター・カンプの『Breakthrough』という本の内容をもとに日本人向けに書き直したものだそうだ。以下に役立ちそうなところをピックアップしておく。
・小手先の技術ではなく、知識の蓄積があるほど、短時間で読めて深い理解と記憶に達する。
・目次によって全体の流れを把握する。
・3段階速読法。第1段階:把握するための流し読み(1冊を10分程度、目次、チャート、図表、キーワード)、第2段階:理解のために、重要と把握した箇所の重点的に読見進め、第3段階:記憶のための熟読。奇跡的にマスターできる速読法はないが、この読み方で能力は確実にのびる。
・速読の障害は、口や心で音を出すこと。
・常に自分の中に5~10個程度のテーマを持って本を読み、引っかかることがある都度1,200字程度の文書を書いておき、それがたまったところで論文とする。
・パラグラフごとにメインアイディアを抑える。重要でない物を読み捨てる。目標と納期を設定すれば、読書スピードは速くなる。
本書は、速読術を説く本ではない(1行を一目で視野に入れて、縦書きの本であれば目を水平に動かすことで読み切る方法の紹介などはあるが)。知識がなければ速読はできないという立場なのである。むしろ、効率よく必要な知識を取り込み記憶するための方法について説明がなされていると考えた方がよい。たとえば、紹介されている3段階読書法についても、このコンセプトの中心は、早い段階で本全体を見極めプライオリティ付けをして、マスターすべきことを絞り込むということにある。そのためのちょっとした方法が書かれている。タイトルに惹かれて期待しすぎると、当然のことばかりで失望してしまうが、説明されていることはきわめて真っ当であり、だまされたとは思わない。
(★ 2005/04)
模倣の殺意/中町信/創元推理文庫
デビューはしたものの第2作が書けなくて苦しんでいる新人作家坂井正夫が7月7日午後7時に服毒死を遂げる。自殺として処理されようとしていたが、編集 者で大物作家の娘と元推理作家のルポライターが坂井の死の真相を求めてそれぞれ同時に調査を始める。2人の調査が1章ごとに交互に記述されていく。
初出1972年ということなので、今では繰り返し使われている手法ながら、当時はかなり斬新であったのではないかと推測される。その時に読む ことができたら、今よりはるかに驚き、繰り返し読んだかもしれない。その意味では、登場が早過ぎたパイオニアには高い敬意を払いたいと思う。
しかし、本作の流れをくむ同工異曲の作品が巷にあふれ、読み手がすれてしまっている状況下での復刊はちょっと苦しいか。このトリッ ク自体が古いわけではないが、記述が30年前のことなので、読み手が妙に身構えてしまい、みずみずしくない印象である。読んで楽しいかという点か らは、少々厳しい評価とせざるを得ない。横浜ランドマークにある本屋で宣伝していたので購入したのだが、本屋のすすめ文句に少しのりすぎたかなと反省。
(× 2005/04)
追憶列車/多島斗志之/角川文庫
5編を収録した短編集。
美佐子は娘の身の回りのものが謎の女に持ち去られていることに気づく。ある日、娘の写真が送られてきたことから、彼女がその女の正体を突き止めようとする「マリア観音」
絵を預けた友人が亡くなり、その後転々とする所有者を追って「絵」を取り返そうとする「預け物」
第2次世界大戦末期フランスからドイツへ疎開する列車の中で日本人少年が出会った少女と連れのユダヤ人の別離のドラマ「追憶列車」
日露戦争の捕虜が収容される松山で逃亡をあきらめないロシア人将校と収容所長の駆け引きとこの将校に幼い好意をよせる姉と巻き込まれながらそれを見守る妹の物語「虜囚の寺」
清水の次郎長の3人目の妻・お蝶が過去の情夫の安否を尋ね始めてから狂い出す運命を描く「お蝶ごろし」
短編としては、あざとい結末の「マリア観音」と落ちがちょっとはずし気味の「預け物」はやや低調だが、時代背景が物語に絡む残り3作は厚みがあって好品。二転三転するストーリーを得意とする著者の長編を期待するとすこし肩すかしを食ってしまうが、長編とは違うテイストが楽しめる。
(★ 2005/03)
報復/ジリアン・ホフマン/ヴィレッジブックス
12年前にニューヨークで残忍なレイプの犠牲者となった主人公クローイは、過去を捨てるため、名前も髪の色も変えフロリダに移り住み、今は州司 法局の辣腕検察官C.J.タウンゼンドとなっていた。ある日、彼女が追っていたフロリダ中を恐怖に落とし込んだ連続猟奇殺人鬼“キューピッド”事件の重要 容疑者が路上でパトロール中の巡査によって偶然逮捕される。予審でキューピッドの声を聞いたタウンゼントは、この男が自分を襲った男であることを確信し、 今日まで癒やされることはなかった悪夢のような事件の心の傷に苦しみながら、連続殺人事件の真相が揺らぐ中、裁判で有罪を勝ち取るべく戦いを始める。
テンポのよさと適度なサスペンスで一気に読ませてしまうエンターテインメント小説である。ちょっとバランスが悪いのは、レイプや遺体の描写で、正 直過度にグロテスクに感じられ、ここまで描く必要があるのだろうかとちょっと疑問。C.J.と同じものを共有することで彼女の苦悩や決断に共感させる ためだろうか?それとも猟奇的なるものを扱うからには、この程度の描きこみがないと今やホラー映画等を通してさんざんグロテスクで残酷なシーンを映像とし て見せられている読み手を惹きつけられないと考えたのだろうか?リアリティと描写の問題として、本作が理想的であったのかどうかはやや疑問なので、もっと 別の解決を見ているサイコ・ホラーでもあればもっと考えてみたい。
キャラクターとしては、主人公のC.J.はよいとしても、恋人となる捜査官のドミニクや相手弁護士ルアド・ルビオが薄っぺらい印象に終始してしまう。特にドミニクは、二枚目でたぶんタフな男という役柄なのだろうけど、ストーリーの中で男女のからみ以上の実質的な役割が与えられていないし、この 男に魅かれることによって主人公の何かが見えるになるようにもなっていない。単なる美男美女のカップル。相手弁護士のルビオはもっと貧困なイメージで、 やり手で美人、時に正義とビジネスの間で悩むというステレオタイプでしかない。この2人以上に重要なのは、容疑者のバントリングがサイコキラーとしての キャラが立っていないこと。粗野で下品で知能指数があまり高くないが、社会的地位を築いた美形で、ちょっと見には女性陪審員から惚れられてしまうよう なキャラクタってどうなのだろう。つぎはぎな感じ。こうした主要登場人物である彼らに対して、秘書のマリソルと彼女を毛嫌いするC.J.の関係は非常にリアルなイ メージを作り出すのに成功している。秘書に対して、ピンクの服を着たデブの死体をイメージするC.J.のモノローグが秀逸である。
ストーリー展開としては及第点でしょう。どんでん返しを示唆しつつそれをストーリーを引っ張るもう一つのエンジンとしており、誰がもう一人 の犯人かということは大した謎ではないですが、C.J.に対するプレッシャーとして利いてくる点は読む者を飽きさせない。米国のサスペンス小説としての 定石はきちんと踏まえられているというところか。
宣伝の引き合いに出されているコーンウェルと比較することはあまり意味があると思えないが、評価を確定するにはまだ2,3冊読むまで留保せざるをえない。
(★★ 2005/03)
陽気なギャングが地球を回す/伊坂幸太郎/祥伝社NON NOVEL
他人の嘘を見抜き、物事の先を読むことができる成瀬を中心に、演説とでまかせの天才響野、人より動物を愛する少年のようなスリの達人久遠、正確な体内時計を持つ雪子の4人はチームで一度も失敗することなく銀行強盗を行ってきた。今回のターゲットは港洋銀行だが、しきりと中学生の息子を心配するなど雪子のようすがおかしい。そして、銀行強盗を決行するが、いつも通り現金を奪取し雪子の運転する盗難車で逃走している途中、別の現金輸送車ジャックの一味と接触事故を起こし、奪った現金を横取りされてしまう。彼らは、久遠が掏り取った携帯電話から犯人グループを探っていく。
ストーリーとしては、クライムノベルお約束の最後のどんでん返しがきちんとなされている。くるぞくるぞという場面でのクライマックスで、いくつかの伏線がきちんと収束している。はずしてきそうなキャラクターと展開だったので直球で来た分、逆にすこし肩すかしであったかもしれない。不思議な読後感。誰にも感情移入させないように構成されていて、リアルな感じがしないように感じる。では、寓話的かというとそういうわけでもなく(寓話性を著者はあとがきで否定している)、もちろん重く残るものもない。
ストーリーのメインストリームと離れたところに、弱くても他人から評価されなくても懸命に生きている人々が、整理されることもなく描かれているのが印象的。この脇役たちの問題は深く掘り下げられることなく放り出されていることで現実味を帯びており(世の中では、それぞれの人にとって他人の問題は常に放り出されたままだ)、それが主要キャラクタたちの厚みのために奉仕している。このあたりの考え込ませないところなどは、エンターテインメントとして潔い。
(★ 2005/03)
マツダはなぜ、よみがえったのか?/宮本喜一/日経BP
本書では、バブル崩壊と同時に経営が傾き、フォード傘下で再生を図っていたマツダの再興の過程が説き起こされる。本書の半分のページが割かれている「製品開発編」はマツダの象徴であるRX-8の開発物語で、エンジニアリングの現場と、経営の現場との激しいぶつかり合いの中から、マツダのモノづくりの神髄が発揮される過程が描かれている。続く「経営・マーケティング編」では、経営の建て直しを、コスト削減、ブランドの立て直し、フォード指導の下での経営改革の3つのプロセスで解説されていく。
マツダの再生のプロセスは、「ものづくり企業」再生の一つの重要なモデルを提示しているといえる。技術なくして製造業の未来はないのはいうまでもないが、その技術は経営なくして、その真価を発揮できないというある意味では当たり前のメッセージが現場と経営のぶつかり合いの中から見えてくる。
しかし、日産のゴーン改革の見えやすさと比較してマツダの経営改革の見えにくさの違いはなんであろうか。それは、本書にあるフォード出身の社長がマツダ創業者の墓参を欠かさないというエピソードに示されているのではないだろうか。フォードは、三つの長いトンネルのそれぞれの時期に合わせ、そのミッションに最適な人材を経営者として送り込んでいるが、そこに共通するのは、創業者に対する敬意であり、それは裏を返せば、損得とは別の会社に対する愛情ではないだろうか(少しひねくれてみれば、愛社精神があることを見せることが重要と考える思考方法。それも程度は異なるが同じことを意味している)。損得抜きの会社に対する奉仕は、外からは見えにくいものである。それが無条件で善である時代は終わったのかもしれないが、人が作り出す「技術」には損得抜きの何かが重要な要素となっているのも真理であろう。
マツダは生まれ変わった。トヨタ、ホンダ、日産など強力な競合相手にはさまれながら生きていく途を見つけ、フォードグループの中核企業になるまでになった。次は、業況が悪化しつつあるフォード本体の改革ということになろう。陳腐な言い回しではあるが、自動車業界の生き残りをかけた競争は一アタマ抜けつつあるトヨタ以外にとっては、終りなき熾烈さを強めている。
それにつけても、三菱自動車のパートナーたる悪名高いドイツ系企業は、フォードとは比べるべくもない。パートナー選びは慎重に。
(★★ 2005/03)
哲学の冒険―「マトリックス」でデカルトが解る/マーク・ローランズ/集英社インターナショナル
SF映画を通じて、哲学の初歩を学ぼうという本である。「フランケンシュタイン」から人の内と世界という外から生じる埋めがたい不条理を説明する。「マトリックス」から自分の存在をどのようにつきとめるのかという内なるものへの確信について説かれる。「ターミネーター」では、心について、二元論の危うさが語られ、「トータルリコール」と「シックスデイ」から自己同一性は何をもって担保されているかが見通される。この調子で「マイノリティレポート」では自由意思が、「インビジブル」では道徳論が、「スターウォーズ」ではニーチェの超人論が解説される。そして最後に「ブレードランナー」で死の持つ意味(あるいは生の有限性の意味)が説かれる。
よく、「おまえの悩みなんか、この宇宙の広さから見ればちっぽけなものだ」というような慰めを聞くが、これにどこか釈然としないのは、第1章をみれば解決する。誰しもが必ず感じるジレンマはこれであったのかと思う。最初の3章分くらいはテーマは違えど、内なる自分と外の世界にひきさかれる人の宿命的な問題が語れていて、非常にわかりやすく、本書の中でも最も楽しい部分である。それと、哲学とよりそうように進歩してきた論理学の発想が随所に論を整える部分に現れていて、議論をベイグにすることなく頭をすっきりさせてくれる(昔々の学生時代に読んだヴィトゲンシュタインの引用も効果的に使われている)。基本的には教科書のレベルを出ないが、一目で分かる哲学のような類の本と比べれば、圧倒的に楽しむことができる一冊である。
本書の中で繰り返しアーノルド・シュワルツェネガーとポール・バーホーベン監督を持ち上げていて、もちろん字義通りでないのだろうと思うが(別に名優名監督だと行っているわけではないので意味は違うのだが)、こういう人を食ったところは我が国の哲学科教授の土屋賢二の書くものみたいである。
(★★ 2005/03)
やっぱり使える「ポスト・イット」!!速読・速解の技術/西村晃/大和出版
この中に書いてあるようにポストイットを使いながら、読んでみる。
読書は一度の精読より数度の拾い読み。初読の際にポストイットを貼りながら読んでいく。重要度に応じてページの貼る位置を変え、必要に応じて書き込みを3色ボールペンで行う(赤青を肯定否定の論調に分けながら使う)。読解の方法は、基本はキーワードの拾い読み。その本を読む際の自分の問題設定を明確にして、それへの答えを見つけていくということで不要部分を読み飛ばす。キーワードは、序章やまえがきに、略語や「」に注意してみつける。重要な部分は前半100ページまでにかならず現れる。発想法としては、分類し再構成することでつかむ。また、手で書き込むことで頭に定着することの重要性についてハイライトされる。
この手の類の中では、かなり実用性の高いものであったが、自分がやっていることとの比較ではそれほど目あたらしくはなかった。こうした方法論は活字で読むことで自分の行っていることの再確認になるのと、独りよがりになっていたり、逆に大胆になりきれない部分を修正してくれることで、役に立つ。それが証拠に、自分が普段まったく行っていないような類のことが書いてあるものは刺激にはなっても、自分の効率を上げてくれることには余り役に立たないことが多い。本書では、2.5×7.5のポストイットを奨励していたが、個人的には読書にはちょっと大きくて使いにくい印象がある。どうなのだろうか。
(★ 2005/03)
退職刑事 2/都筑道夫/創元推理文庫
退職した刑事の父にその息子の現役刑事が一風変わった事件について相談するというスタイルの「安楽椅子型探偵」譚。自殺と処理されつつある事件の真相と遺書の謎を解く「遺書の意匠」、自首をしてきた殺人事件の重要容疑者がいたホテルの部屋から女の死体が発見される「遅れてきた犯人」、被害者の右手の爪だけがきれいに切られていたのはなぜか「銀の爪切り鋏」、毎晩深夜の定時に駅に現れていた女が殺害される「四十分間の女」、新婚旅行中に浴室で殺された「浴槽の花嫁」、厳冬の日本海の海岸で水着姿で発見された理由を追求する「真冬のビキニ」、結婚式の花婿控え室で衆人環視の前での花婿事件「扉のない密室」。
探偵の設定はなかなかに自由度が高く、面白い設定である。ただ、安楽椅子探偵ということであれば、ホームズの時代であれば別かもしれないが、あとはよほど事件が奇想にとんでいないとだれてしまう。本短編集は、魅力的な謎を提示することには成功しているといえるが、それをたった一つの真相に収斂させるところに鮮やかさが弱く感じられる。つなぎ合わせた事実が真相を物語りきれないのである。その意味では、好みで言えば、「扉のない密室」がなかなか秀逸。次点は「銀の爪切り鋏」。「四十分間の女」と「真冬のビキニ」は謎が魅力的であるのに、結末が妙に説明説明してしまっていたり、不自然さを感じさせない思い切りに欠けているように思える。
(× 2005/03)
阿弥陀(パズル)/山田正紀/幻冬舎文庫
残業帰りの恋人同士の一方がカメラに監視されている深夜のビルから消えてしまう。ビルの警備員と風水火那子がこのなぞに取り組む。
私の中では山田正紀は『神狩り』『弥勒戦争』などのSF作家である。SFというセグメントが失われてしまい、本格SF作家がミステリー作家となってしまったのは、プラスの面がないとはいえないが、一抹の寂しさがつきまとう。そういう目で見てしまうからだろうか、どうも文体が媚びているように見えて、悲しくなってしまう。しかし、ミステリーとしての骨格はさすがである。人の消失トリックもさることながら、動機が説得力のあるように伏線を張っているところも、SF作家として稀代のストーリーテラーの面目躍如であった。これからしばらく『ミステリオペラ』に至るミステリー作家山田正紀を追ってみようかとも。
(× 2005/02)
悪の読書術/福田和也/講談社現代新書
書物と付き合うことでスタイルが生まれてくる。そのためには本との間に緊張感を生じさせるとともに他者の視線を導入することが重要で、それを社交的読書と著者は呼び、かかる視点から様々な作家と書物を分析する。また、読書を含めてあらゆる鑑賞行為には、スノビズムとナルシズムがつきまとうが、このスノビズムによって、人は判断されてしまう。だからイノセントに読書に楽しむのではなく、スノッブな意味での社交的向上を考える必要があり、それを考えるということは文化の位相・格差を認識することになる。
読者を挑発する書きぶりで、作家の価値をスノビズムの視点で批評しながら読書の質を問う。もちろん、見方が一方的に過ぎるのではないかとカチンとくる部分がある。だが、それはおそらく著者の戦術にはまっているのだろう。
彼が『作家の値打ち』で高く評価している矢作俊彦が、成熟と非・成熟の間にあるように思え、彼の本書での見方と一致しているのかわからないが、そこに彼の客観との偏差があるように見える。
ベートーベンの音楽は個性の表現、バッハは普遍的音楽という話が出てくるが、これは面白い。過去に、文学史や作家論を学んだときに、なぜ作家の行動、生活や人間関係まで見た上でその作家を論じなければならないのか理解できなかった。作家の産み落とした作品は作家から切り離れて普遍的価値があるのではないかと。著者が作家の顔を考えるところで指摘するように作品と作家が不可分一体で考えられるようになっていることは確かである。そのこと自体は完全に納得してきたわけではないが、ベートーベンとバッハで説明したのはちょっと目からうろこであった。
(★★ 2005/02)
金融アンバンドリング戦略/大垣尚司/日本経済新聞社
80年代以降米国では金融技術が劇的に進展し、90年代以降それに伴ってビジネスモデルを変革させていったのに対し、日本の金融セクターは、米国発の金融技術革命には対応してきたものの、その技術を活かすための経営方法を変革させることはできずにいた。本書は、こうした金融界の新しい経営の枠組・ビジネスモデルを提案するものである。その考え方のコアにあるものは、業態縦割り型の現在の構造を変えて、重複した経営資源を効率化することを前提に、機能ごとにセクター構造を見直し、オリジネーション、サービシング、マニュファクチャリング、リスク管理、資金調達といったブロックごとにアンバンドリングを行っていくことが重要であると説かれている。
軸のぶれない骨太の金融セクター改革の書である。わが国の製造業が日々技術の革新を行っていくとともにそれを活かすための経営のあり方を不断に模索しているのに対して、明らかに金融の経営は遅れている。私も金融セクターのはしくれに身を置く者としてそれは痛感する。本書の中でも冷静に批判されているように、規制緩和に抵抗する民のプレイヤーの改革へのブレーキが常にあり、このままでは金融セクターは緩慢な死を迎えることになりかねない。
マイナス財としての金融商品の特徴、管理型信託会社を活用した新ビジネス、プロジェクトマネジメントの重要性、勝負の決まっていない合併の不安定性やビジネスモデルの変革なき公的金融機関の民営化のリスクなど、どこをとっても知的アピタイトを満たす書であった。
(★★★★ 2005/02)
ソシュールと言語学/町田健/講談社現代新書
ソシュールが挑んだ言語の本質とその後の展開が非常に簡潔に解説された本である。ソシュールは、言語行為をラングとパロールに分割し、言語学の対象をラングに限定する。これは意味を話し手から聞き手に伝える社会的な約束のことである。ラングが伝達するものは記号であり、記号はシニフィアン(表示部、意味するもの、知覚できる音や図形の集合)とシニフィエ(内容部、意味されるもの、事柄または事物の集合)の対であるが」、両者は恣意的な結びつきでしかない(第一原理「言語記号の恣意性」)。言葉とは単語が一定の規則に従って一列に並ぶことで意味を表すもの(第二原理「言語記号の線状性」)。この原理に従えば、あるひとつの単語の意味を決めるには他と違うということを考慮しないといけないことになる。つまり、言語には、単語の意味を他の単語との関係で決定する「体系」がある。「体系」内の要素の価値(意味)を決める要素(単語)が線状に並べられて、形成される「構造」にソシュールは言語の本質を見出した。
このソシュールの思想は継承され、音素分析のプラハ学派、関係性を重視し「言語代数」という手法をとるコペンハーゲン学派、事物から音声への過程こそが言語の本質とする言語過程説の時枝誠記、具体的な言語事例を構造主義的に分析したバンベニスト、言葉の変化を経済性で分析する機能主義のマルチネなどが紹介される。
構造主義の源流をたずねてみようと思って読み始めた。内容は、構造主義そのものへの理解を深めるような種類のものではなく、人間の最も人間たる所以である「言語」を人々がどのように理解し尽くそうとしたかの格闘の歴史が記されている。
コトバを記号と位置づけ、そこに実相がないとし、その意味するものとは完全に恣意的な関係となっており、意味はコトバの体系の中で初めて規定されるとしたことはソシュールの輝かしい成果である。しかし、ここから彼とその後継者たちが、普遍的な公理のみに基づいて科学的に言語を解明していこうとすることで、大きな壁にぶつかっていった。実際、本書のソシュール以後の展開を読めば読むほど、言語学としての分析はソシュールの偉大な発見以降大きな進捗を見ていないように思える。もしかするとまったく別のアプローチが必要なのかもしれない。新たな天才が現れないと。
(★★ 2005/01)
オーデュボンの祈り/伊坂幸太郎/新潮文庫
ささいな事情からプログラマをやめて失業中の伊藤は、コンビニ強盗を行ない、古い知り合いの悪徳警官に逮捕されるが、逃亡を企てる。朝、気がつくと、彼は、誰も知らない小島へと連れてこられていた。その不思議な島では、口をきくことができすべてを見通すカカシ、人を殺すことを認められた男、嘘しかつかない男、太りすぎて動けなくなった女、死にいく者の手を握ることを職業とする女など風変わりな人々が、風変わりなしきたりで暮らしていた。そんな中でカカシが殺されてしまう。誰がこの島の人々に敬愛されていたカカシを殺してしまったのか。
小説は何でもできるのだ。そして、その中の手法的分類であるミステリーでも。設定がはまった瞬間にこの小説は小説として成立したといえよう。伏線がよく効いているという話を聞くが、伏線のおき方はそれほど巧みとはいえないし、それが結実した効果も大きくは驚かせてはくれない。それはやはり、あらかじめ伏線がすごいよと知ってしまったからなのだろう。残念。
ところで、「逃げる」主人公・伊藤は一体どう変わったのだろうか。コンビニ強盗をして人生をリセットしようとした彼、幼い頃から自分の手に負えない悪漢城山を結局、桜の手によって消し去った彼は、一体どのように成長したのだろうか。彼女の静香はこのおかしな経験を通して変わったかもしれない(少なくとも変わるチャンスはあった)のに、私たちの世の中の映し鏡ともいうべき荻島の奇妙な生活で何を得たのだろうか。別にミステリーなのだからそんなことどうでもよいのかもしれない。誰もシャーロックホームズやエラリークイーンの成長譚など彼らの小説に求めていないのだから。しかし、本作のもったいぶった人生に対する警句の数々は、では何のためにあったのだろうか。これらは何かの伏線ではなかったのか。そう、伏線がすばらしいという評価に対して素直にうなづけないのはそうしたことも理由になっているのかもしれない。
ところで、カカシが考え、話す原理が秀逸。
(★★ 2005/01)
情報と国家―収集・分析・評価の落とし穴/江畑謙介/講談社現代新書
情報収集についての手法の紹介に始まり、公刊情報の持つ価値、インターネット、エシェロン、衛星写真、そして人的ソースによる情報(HUMINT)まで、その収集方法による情報の特徴が説明され、情報収集とは如何なる作業をすることなのかを明らかにする。次に情報の分析の核心が、イラク戦争をめぐる米国・イラク等の情報分析を例に解説される。最後に他国からもたらされたような情報をどのように評価していくのか、北朝鮮をめぐる情報をどのように評価すべきであったのか詳しく論じられる。
まさにタイトル通り国家戦略上必要不可欠な行為である情報の取り扱いについて論じた書である。軍事オタク的要素を取り上げる局面はほとんどなく、きわめて冷静に情報戦を分析しており、著者の容貌からうける印象とは異なる確かな議論の積み重ねで構成されている良書である。特に感銘を受けるのは、インテリジェンスとはその状況における最良の推測であればよく、真実である必要はないというくだり(マイヤー統合参謀本部議長の発言の引用)である。これは冷徹な現実を言い表している。しかし、最良の推測であるべく努力する必要があり、真実でなくてもよいというところに逃げてはいけない。
また、情報の評価は、常識と専門知識を駆使せよという部分も、仕事上の判断で迷ったら最後は常識に頼るべきであると私も常々考えていたため、インプレッシブであった。イラク戦争時に、結論ありきで上司の気に入るような情報を挙げてくる部下の姿勢について記されていたが、いずこも同じ宮仕え、その心情はよくわかるよと妙なところで感心。
(★★★ 2005/01)
アメリカ過去と現在の間/古矢旬/岩波新書
本書では、米国を理解するための基本的なコンセプトが歴史的な成り立ちから解説されている。まず、米国の対外行動の論理を二つの軸、孤立=国際(介入)主義、理想=現実主義について建国以来の背後の思想(すべての思想の出発点である古い国家であるヨーロッパから独立したという事実の持つさまざまな意味)から説き起こされる。第2に、「帝国」としての米国が思想との関係で解説され、第3にその「帝国」を支える戦争の指導者としての大統領のシステムが議会の制約との観点をもって語られる。最後に、保守主義(人の自由をいかなる意味でも制約しない社会を希求する)の変容と現在のネオコンにつながる一連の流れが解説され、それとある意味不可分の問題であるところの宗教的側面、キリスト教福音主義の思想と「原理主義」についてのの解説でまとめられている。
内容的には教科書的であって、決して目を見張るような分析がなされているわけではないが、こうした歴史に重きが置かれた定説を抑えておくことは、ちょっと退屈だが非常に重要である。本書に書かれていることについての理解だけでもずいぶん米国内の政治的な動きの見通しがよくなる。近代になり「古い欧州」からの独立によった建国とそれを支えた精神が米国という特異な若い国に及ぼしている影響が大きく、他のどこの国よりも強く原点に回帰する傾向がある(いわゆる原理主義的な傾向)というパースペクティブはわかりやすい。
もちろん政治には、人の要素と経済の要素がからみあってより複雑な諸相をみせるので、この思想のスケルトンに肉付けをする作業も行う必要があるのかもしれない。
(★★ 2005/01)
愚か者死すべし/原尞/早川書房
銀行強盗事件で警察に自首した伊吹哲哉の娘啓子は渡辺に依頼するために沢崎の事務所を訪れた。伊吹は横浜へ移送されることとなり、啓子を新宿署に送り届けた地下駐車場で、沢崎は、伊吹と刑事が銃撃される現場に居合わせることになる。伊吹は軽傷ですむが、刑事は殉職する。調査を進めた沢崎は偶然別の老人の誘拐事件にも巻き込まれていく。
年をとっていくと物事を単純に考えようとしがちであり、それはその人の覚悟次第では円熟であったりもする。沢崎も年をとり、さまざまな人間関係や事件を経て、今回の状態に至っているのであろうが、彼の若き日の活躍譚と比べるとひっかかりがなく、するすると読めてしまう。これは、円熟なのだろうか、それとも老いに由来する現実からの距離感なのだろうかとつい考えてしまう。
また、時代批評的なエピソードが適度にちりばめられているが、かなり中途半端な印象で終わってしまうのは残念。このあたりはストーリーと抜き差しならぬ関係で描かれた矢作俊彦の昨年出た新作『ザ・ロング・グッドバイ』と比較するとだいぶ見劣りしてしまう。
(★★ 2005/01)
| SEO | [PR] おまとめローン 花 冷え性対策 坂本龍馬 | 動画掲示板 レンタルサーバー SEO | |
